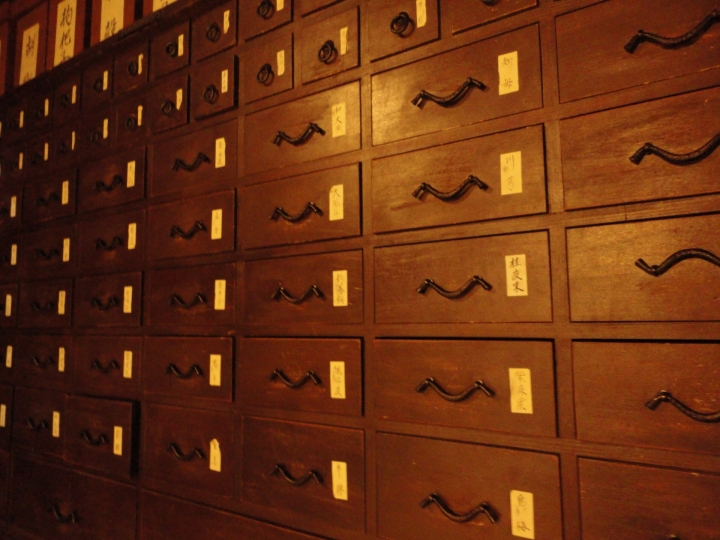当サイトでは「建築の納まり図とその開設」というタイトルそのままですが、建築の納まり図を色々と紹介していこうと思っています。
建築の納まりを色々と紹介して…と言いつつも、これから紹介していこうとしている内容を考えると結構気が遠くなる思いもあります。
自分の中にある知識を全部アウトプット出来るものなのかどうか、という心配ですね。
建物には大きな区分で言うと「床」「壁」「天井」という区分があります。
もちろん上記のカテゴリーに入らないものもありますけど、基本的には建物を構成する要素としては上記の三種類が大半を占めます。
そしてそれぞれの要素で色々な仕上材が用いられています。
また、それぞれの部位が切り替わる部分のパターンもたくさんあるので、情報量としては結構膨大になってしまうかも知れません。
ということは、記事を書く私も結構大変かも…
と、説明する前から心配ではありますけど、少しずつ記事を増やしていこうと思っているのでどうか時々覗いてみていただけると嬉しいです。
まずは当サイトのテーマである「建築の納まり」について少し考えてみると…
大抵の方は日常的に色々な建物に出入りしている訳ですけど、例えば買い物などに行った場合でも、壁た天井の納まりがどうなっているかをじっくり見たりはしないと思います。

だってそんなに興味があるものではないし、建物が完成してしまえばそれはもう当たり前の風景になってしまうので、そこに注目するのは建築関係の仕事に就いている方だけでしょう。
私も若くて経験が少ない時代には結構色々な建物を見て歩きましたが、経験を積むにつれてそういうことは自然としなくなりました。
これはもう本当に基本的な話で、建物は鑑賞するものではなくて利用するものだ、ということなのでしょう。
建物に入るなり天井をじっくりと観察し始めるとか、ちょっと挙動不審過ぎますし。
ただし。
そうして使う側にはあまり細かい部分まで見てもらえないとは言っても、その建物を設計する側としては、かなりのパワーを使って建物を設計しているものなんです。
これは恐らくどんな設計者でも同じでしょう。
壁・床・天井その他様々な仕上材を、自分のセンスと経験とポリシーと、あとはコストなどを含めて総合的に検討して決めているんです。
その結果どんな見え方になるのかを想像しながら。
こうした地道な作業はかなり奥が深くて大変だし面白い訳ですけど、当サイトではその奥深さと面白さを少しでも読んで頂ける方に伝えていくことが出来れば。
そんなことを考えながら地道に説明文を書いています。
仕事で建物をどのように見せるかを色々考えていて、仕事が終わってからこうして建築の納まりについてやっぱり色々と考えながら説明をしていく。
どちらも地道に進めていく必要があるもので、私はそうした作業が好きなのだと思います。
と、私の個人的な好みはさておき、当サイトでは納まりの図面だけではなく、様々な仕上げ材のメリットとかデメリットなども色々書いていくつもりでいます。
仕上材というのは時代によって少しずつ違ってくるものなので、数年が経過すると当サイトの内容も少しずつ古くなっていくことになります。
でも全然、全く納まりの方針が変わるということはないので、基本的な知識を得ることが目的であれば、ある程度月日が経過しても問題はないと思います。
もちろんこれから開設していく全部の記事をくまなく読む必要はなくて、今の自分に必要な内容だけをピックアップして頂くのが最も効率的な使い方です。
そのため、当サイトの記事はカテゴリに分けて色々と分類してあります。
自分が必要としている内容に合ったカテゴリに進んでいき、そこから必要な知識をとりだして自分の知識としていく、というような使い方がおすすめ。
なるべく図とか図面とか写真などを入れて読みやすく、そして出来る限り分かりやすく説明をしていきますので、ちょっと気になる記事だけでも読んでいただければ嬉しいです。
■コストと仕上材について考える
先ほど、どのような建物を造るのかを考える役割の設計者は、自分のセンスなどの他にコストも考慮して設計をしている、というような話を取り上げました。
コストを意識しながら設計をするのは設計者としては少し寂しいことで、本当はコストを考えず、最高の仕上材だけをピックアップして決めたいところです。
しかしビジネスでコストを意識することは当然のこと。
コストを考えないでやるのは仕事ではなく単なる趣味の世界だし、そもそもコストを意識しないで建物を設計することにニーズはありません。
ですからこれはもう仕方がないことだと言えるでしょう。
それに、建物全体を計画した際に、全ての場所で最高級の仕上げ材を使うとか。
それは確かにたくさんお金が必要にはなりますけど、そうやって出来上がった建物が最高なのかというと、まあそうとも言えない訳です。
たくさんお金をかけることと、良い建物とは必ずしもイコールではないということです。
もちろん建物のグレードとコストには密接な関係があることは間違いないですけども。
例えば最も身近な建物として一戸建て住宅を考えた場合、押入れの奥の壁に桧の無垢材とかを採用しても、ほとんど見られることがないのでやっぱり勿体ない訳です。
それならば玄関のグレードを上げた方が効果的にコストを使ったことになるはず。
商業施設の設計をする場合でも、例えばスタッフさんが使うバックヤードとか、常に荷物が入っている倉庫の壁に石を張っても宝の持ち腐れです。
石には美しい模様や質感があるので高級感出る仕上材なのですが、石仕上面は大量の荷物に隠れてしまい誰にも見えないことになってやっまり勿体ない。
下手したら台車が当たってしまい石が割れてしまう可能性も。
なのでやっぱり石の壁は建物の顔と言えるエントランスホールなどに使うのが良い、という当たり前すぎる結論になってしまいます。
これらは少し極端な例ではありましたが…
建物を設計する場合にはやはりコストパフォーマンスも意識しつつ、適切な場所に適切な仕上げ材を使っていきたいものです。
このあたりの話は結構重要な部分でもあるので、今後具体的な納まりの説明をしていく中でも出てくる話だとは思います。
…が、色々な話をしていく前にまずお伝えしておきたかった内容でした。
■建築の納まり
そうして色々な要素を検討していき採用されることになる仕上材ですが、ここからも結構難しいところがあります。
今までは方針を決めていく苦労で、その後はその方針を具体的な形にする苦労、というような感じですね。
そして当サイトで取り上げたいのはどちらかと言うと後者、それぞれの仕上材が具体的にどのような関係で納まっていくのか、という部分です。
建築の各所で使われる仕上材は、その部位や材料によって厚みも固定方法も様々なので、結果として非常に多くのバリエーションが存在するんです。
どの仕上げ材を採用したかによって、そこに必要な壁の厚さなどが変わってくる訳です。
そして当然、採用した仕上材を固定するための下地位置も仕上材によって大きく変わってくることになって…とかを色々と考えていく必要があります。
このあたりが建築の納まりとしての奥深いところで、なおかつ面白いところでもあります。
それが難しい場合も結構ある訳ですけど、だからこそ面白いんじゃないかと。
こうした部分に面白みを感じるためには、まず色々な仕上材ごとの納まりを知識として知っておく必要があります。
そうした知識がないと検討も出来ないですから。
当サイトでは、建築関連の仕事に携わっている方、そしてこれから建築に関する仕事に携わりたいと思っている方に対して、様々な納まり情報を提供していきたいと思っています。
少しでも読んで頂ける方の知識にプラスになるよう、細かい部分を含めて色々と書いていきますのでどうぞよろしくお願い致します。