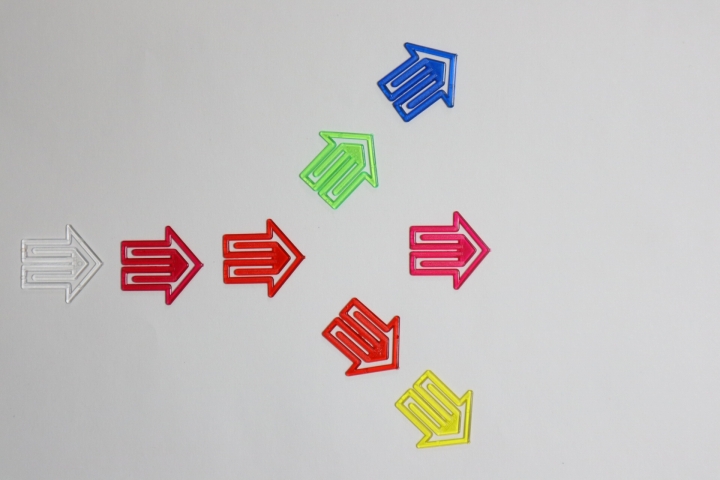設計者が設計図をまとめて発行したあとで、建物は施工段階へと進んでいく訳ですけど、施工段階では設計者が建物の細かい納まりにどのように関わっていくのか。
そのあたりの話を前回は取り上げました。
設計図が示す建物の基本方針というのは非常に重要で、それがコストや工期などのベースになる、ということは間違いありません。
しかし施工段階で作成される施工図や製作図も、実際につくっていく建物の内容と正確にリンクする訳ですから、やはり設計図と同じくらい重要なんです。
そうした施工図や製作図の内容をチェックして、自分たちの要望をそこに盛り込んでいきつつ精度を高めていくことで、建物のクオリティも高まっていく。
そんな流れで設計者は施工段階に関わっていくことになります。
ほとんどの意匠設計者は、建築の色々な部分の細かい納まりについて、どのように納めたいかという考えを持っています。
まあ私が知る限りの設計者は、という条件が付いてしまいますけど、意匠設計者が意匠を気にしないはずはないですよね。
そう考えると、建物の様々な部分について細かい納まりを気にするのはプロとして当然、ということになってきます。
そして、自分がプロとして気にするくらいですから、様々な場所で色々な納まりのバリエーションがあるのかの知識も豊富。
これが一般的な意匠設計者の姿ではないかと思います。
■納まりに正解はない
納まりにこだわりを持っている意匠設計者とは言っても、実際に建物をどうやって納めていくのかという部分で、人によって色々と好みが出てきます。
これはかなり当たり前の話ですが、担当する意匠設計者の好みによって建物をどのように見せたいのかというのが少しずつ違ってきます。
色々なやり方がある中で、どのやり方を選択するのかは意匠設計者の好みと、そして施工者側の考え方によって変わってくる訳です。
そしてどのやり方であっても、最終的にはある程度綺麗に見えてくることになります。
つまり納まりには「これが正解」というものはない、ということですね。
「こうしておけば間違いない」という正解があると仕事は非常に楽になるんですけど、もしかしたらそれは楽なだけで、あまり面白いとは言えない仕事になるかも知れません。
もしそうなったら、正解を集めた資料さえ持っていれば誰でも同じ仕事が出来ることになって、私は仕事がつまらなくなってしまい困ると思いますが…
まあそんなことはあり得ないから気にしなくても良いかな。
納まりには絶対的な正解はないですけど、トータルでどう見せるかなどを考慮して、最終的に美しく見えればどの選択肢も正解のひとつだと言えます。
時には「明らかにこれは不正解だよな」という場合もありますが、まあ人間がやることですから失敗もありますよね。
そこが建築の難しいところというか奥が深いところというか、そういう部分が納まりの面白みではないかと思います。
もしこれから建築関連の仕事に就こうと考えている方がいたら、そうした面白さがあるということをここでは伝えておきたいです。
ところで、そうした納まりの考え方を持っている意匠設計者に対して、施工段階で細かい打合せを行っていく施工者の視点はどうなのでしょうか。
■施工者の視点
意匠設計者が建物の見た目を重視して納まりを考えるのと比較して、実際に建物を施工する施工者側が建築の納まりについてどのような視点で考えるのか。
これは当然のことながら、意匠設計者が優先する項目とは少しだけ違って、もっと別のことを優先している場合が多いです。
もちろん綺麗に納めて質の高い建物をつくっていく、という方向性は意匠設計者と同じですけど、そこに幾つかの要素がプラスされるんです。
・コストを出来るだけ低く抑える
・施工出来ない納まりは選ばない
・建物が運用された後のことも考える
こちらも私が知っている限りの施工者は、という条件が付きますが、コストを意識しない施工者というのはちょっと存在しないんじゃないかと思います。
施工者側はビジネスとして建物を建てる仕事を請け負っている訳ですから、その中で一定の利益を挙げなければならない、という使命があります。

だからこそコストを意識して仕事をしている中で、意匠設計者がやりたいと思う納まりを全部そのまま実現してくれる訳ではないんです。
見た目を美しく仕上げていくためには、どうしても見えない部分にお金がかかる場合も多く、そうなると施工者として簡単にOKと言えない場合も多いんです。
設計者が発行する設計図に記載されている内容であれば、それは施工者として見積もりに入れておくべき項目になります。
もしそうであれば、いくらそのためのコストが高くついたとしても、その予算は確保しておかなければいけない種類のものということ。
だからそこは設計者が押せる部分です。
しかし、設計図に記載のない部分の納まりをどうするか、という状況では、施工者は出来るだけコストを抑えた納まりを提案してきます。
施工しやすくてなおかつコストがかからない納まりが、そのまま意匠設計者が喜ぶ見た目になるとは限らない訳です。
これは「施工者は基本的にデザインには興味がない」とか、そういう種類の話ではありません。
施工が守るべき項目の中には当然「コスト」も入っているので、施工者の立場から出来るだけコストを抑えたいという気持ちになる。
そこを守った上で出来るだけ高い品質の建物をつくっていきたい、という優先順位があるので、そこで意見が違うのはある程度仕方がないでしょう。
そこは意匠設計者と施工者とで単純に立場が少し違うだけの話で、決して悪いことでも何でもないことなんです。