建物を建てるプロジェクトを進行する際には、設計者と施工者という異なる役割を持つ人、会社が協力することになります。
そして、設計者と施工者が建築の納まりについて考える時には、お互いに少しだけ重要視している部分が違っている。
前回はそんな内容の話をしてみました。
「より質の高い建物を造る」という基本的な方針は、設計者であっても施工者であっても全く同じだと思います。
しかし主にコストや工期、そして施工性などの現実的な要素があって、設計者と施工者の立場は少しずつ違ってくることもあります。
このあたりの微妙な話は、私が今まで仕事で経験してきた中での感想が多く入っているので、違和感を感じる方もいらっしゃるかも知れません。
なのでこうした話はここで終わりにしておき、概要的な説明からもう少し具体的な話に進んでいくことにしましょう。
今回は最後のまとめということで……
結局のところ、設計者と施工者のどちらが納まり詳細を必要とするのか、というあたりについて考えてみます。
■設計者でも施工者でも学生でも
今まで建物をつくっていく役割の分担として、設計者と施工者という区分をしてきましたが、結局はどちらの立場であっても細かい部分の納まりを気にすることに違いはありません。
建物を現在進行形で建てている真っ最中にも関わらず、建物がどう見えるのかという納まりを全然気にしないのであれば、その方はもはやプロとは呼べません。
まあそういう人は実際にはあまりいませんけど。
建物の部位別に細かい納まり詳細図集みたいなものがあって、ある程度その納まりが標準になっていれば、設計者も施工者も必要な時に活用するのではないか。
そこから先は色々なパターンによって少しずつ変えていくことで、標準図としての役割を果たすのではないか。
これが当サイトを作成している私の考えで、なおかつ当サイトがそのような詳細図集として機能することが出来ればという期待です。
そうした内容を表現するために、今まで設計者と施工者の立場について、そこそこ長い説明を続けてきました。
出来れば、設計者・施工者どちらの立場の方にも、当サイトが掲載する納まりを参考にして頂ければ良いなと思っています。
そして、今のところそのどちらにも属していない学生の方にも。
学生の方には納まりだけではなく、設計者や施工者の役割なども知って頂き、自分が将来どのような仕事をしたいかなどの参考にしてもらいたいです。
もちろん当サイトの内容だけでは不足ではありますけど、少しでも自分の中の知識を増やしていくために役立てればと思っています。
私が学生の頃に細かい納まりについて解説しているサイトがあれば良かったんですけど、残念ながら本でしかそういう情報を仕入れることは出来ませんでした。
もちろんそうした本をたくさん買って勉強はしましたけど、充分な知識を得ることは正直言って難しかった。
そういう意味では、ネット上で簡単に求めている情報を入手することが可能な今は、非常に便利な時代なのかも知れません。
逆に、自分が持っている知識を情報として発信できるというのも良いですよね。
■選択肢が多い方が有利
建築の納まりは様々なバリエーションがあります。
そしてこれが困ってしまうんですけど、「基本的にこれが絶対に正解」というものはない、という話は以前も少し紹介した通りです。
建物の各所で出てくる「ここをどう納めるか」というのは、色々な選択肢があるけれど、完全な正解なないんですよね。
「さすがにこれは駄目かも知れない」みたいな不正解はあるんですけど、その逆はなかなか存在しないのが困ったところなんです。
どこかに絶対の正解があるのなら、それをきっちりと覚えれば良いだけの話なんですけど、そんな正解の暗記作業を続けたとしても驚くようなデザインとかは絶対に見つからないはずです。
納まりというのは、そんなに単純じゃないんですよね。
そうなってくると、まずはいくつかある選択肢の中からベストだと思える納まりを選んでいく、という感じで進めることになります。
一般的な部分にで使われているオーソドックスな納まりというのは確かにあるので、そこからまずはスタートしていくのが良いのかなと。
設計者であっても施工者であっても、基本的には同じような手順で納まりを検討して調整していくことになります。
そうした場合には設計者であれ施工者であれ、納まりのバリエーションをたくさん知っている状態の方が絶対に有利です。
納まりのバリエーションをたくさん知っていること、つまり納まりの選択肢が多いということです。
納まりの選択肢が多ければ、その中から今回の場合にはどれがベストなのかを考える際に、より正解に近い選択が出来るはずです。
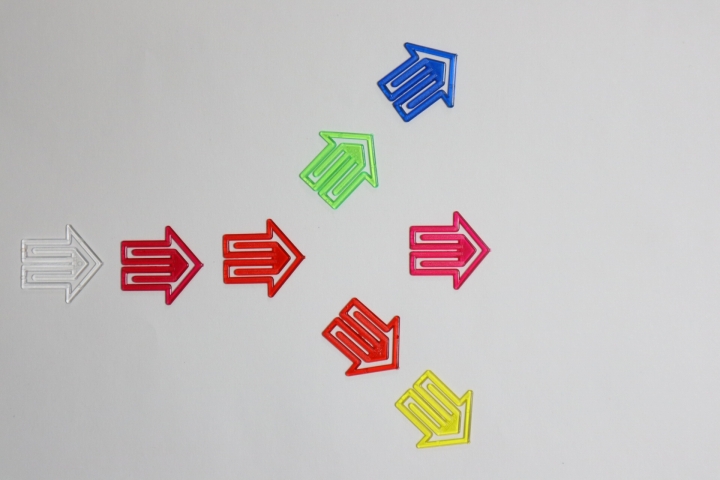
一般的な納まりを知ることと、様々な納まりのバリエーションを知ること。
これが出来れば、建築の細かい納まりをどうするか考える際に、色々な選択肢を検討することが出来るはずです。
もちろんこれは簡単に出来ることではないし、だからこそそこには価値があるのだとは思います。
そうした価値があることの為に当サイトが少しでも役に立てれば、という感じで色々と納まりを紹介していこうと思っています。



