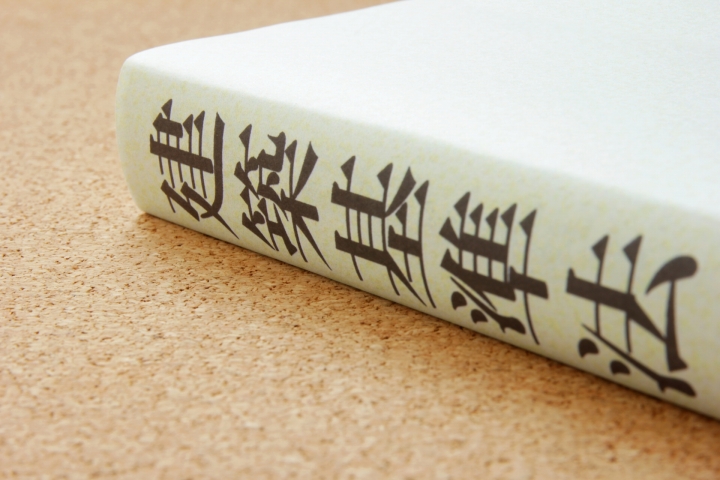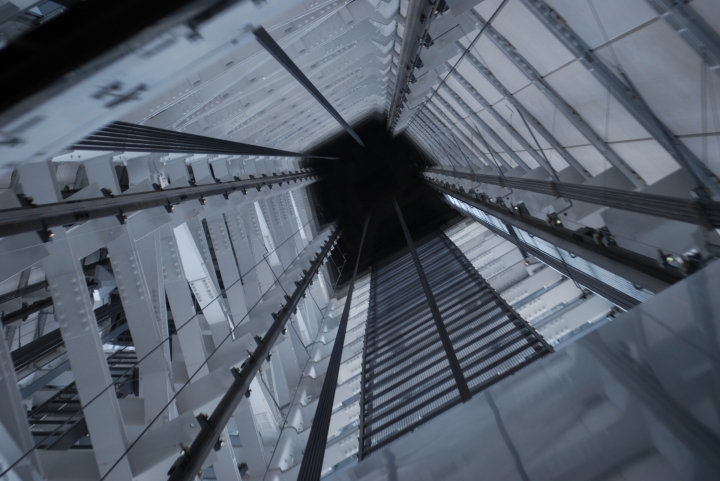建物を快適に利用するため、部屋によっては周囲の部屋から音が聞こえない状態、あるいは聞こえにくい状態をつくる必要があります。
例としては、トイレの中で発生する音が廊下などに聞こえないようにとか、機械室に設置している音が廊下に漏れないようにする等です。
その逆パターンとして、その部屋から発生する音が周囲の部屋に聞こえないような状態が欲しいこともあります。
これは例えば楽器を演奏するスタジオなどがそうした部屋に該当します。
こうした少し特殊な部屋を囲う壁というのは、コンクリートの壁を採用するか、もしくはLGS壁の中でも遮音性能を持ったものを採用します。
質量の大きい壁は音を通しにくいという性質を持っていて、だからこそ重量のあるコンクリートの壁には遮音性能があるんです。
しかしコンクリートの壁はやはり壁が厚くなってしまうので、出来るだけ広くスペースを取りたいと考えた場合は遮音性能を持っているLGS壁を採用することになります。
このあたりの判断は設計者の役割で、遮音壁が必要な部屋をどのように配置していくのか、設計をする段階できちんと検討していくことになります。
もちろん建物を建てる施主の考えも重要になってくるので、施主の要望をヒアリングしつつ、意匠的な意図なども考えていく訳です。
そうして最終的には色々な要望を満たしたプランを練りあげていく。
ここまでが「設計」ですね。
そして、設計段階で色々と計画をしてきたプランを実際に造っていく。
求められている性能を満たした壁を実際につくっていくために、どうやって壁を納めていくのか、という検討はそれから結構後のステップになります。
これが「施工」段階です。
もちろん設計段階での検討も重要になってくるはずだし、きちんと納まるとうに検討する施工段階での検討もそれと同じくらい重要です。
設計者の検討と施工者の検討が合わさってはじめて、建物を建てようと考えている施主が喜ぶ建物の完成が見えてくることに。
こうした話は遮音性能を持った壁とかに限った話ではなく、あらゆる項目で言えることなので、ここで改めて書くのも変な感じですけど…
そのようにして建物の計画は進んでいくことになります。
さて…
今回はLGS壁についての話の続きということで、遮音よりもさらに重要な性能である「耐火性能」について簡単に説明をしていくことにします。
■デザインよりも大事なこと
ある程度の規模をもっている建物では、万が一その建物の中で火災が発生した場合でも、中にいる人が安全に避難できるようにという法的な決まりがあります。
設計者は基本的に建築基準法に沿った建物を設計する義務があるので、当然そうした決まりを守ることを前提にして建物は設計されていきます。

もちろん法律に沿った建物をつくるのは建築に携わる者の責務です。
しかしそうした建築基準法という話以前に、建物を利用する方の命を危険にさらすような建物はつくるべきではないですよね。
まずはそういった考え方をベースにして建物は設計されなければなりません。
建物の見た目ということでデザインも大事な要素ではありますけど、それよりもはるかに大事なのが建物を利用している人の安全、そして命です。
それを満たしていない建物は、いくら優れたデザインであったとしても、建物としては失格ではないかと思います。
…というのは私の個人的な考え方で、それを全員に強制するつもりは全然ありませんが、まあ一般的な考え方だと思います。
もちろんデザインも建物の重要な要素なので、それを軽んじるつもりは全然なくて、大事なのは両方を満たすようなバランスです。
ただ、厳密な決まりがない限り、そのバランス感覚は設計する側の考え方によって大きく揺れてしまうことになります。
それでは困るので、建物を設計する側がデザイン重視になってしまわないように、建築基準法できちんと必要な性能が決まっています。
これは考えてみれば当たり前のことですよね。
■耐火性能が必要な壁
ここで急に建築基準法などの話をしたのは、LGS壁の中で耐火性能が求められる場合というのが、こうした法律によって定められるものだからです。
建物の用途や建てる場所、規模などの条件によって色々と変わってきますが、一定の規模以上の建物では必ず耐火壁が必要な条件が存在します。
建築基準法によって定められた条件によって、一定の範囲を超えない面積を耐火性能の壁で区画していく必要がある、というような決まりです。
こうした面積の規定というのは、仮にその建物で火災が発生したとしても、その火災が一定時間以上外部に燃え広がらない為にあります。
その間に建物利用者は建物の外に避難する、という考え方ですね。
また、例えば階段のように建物の下から上まで繋がっているような空間は、その周囲が簡単に燃えてしまわないような処置が必要です。
そうした造りにしておかないと、火災時に発生した炎が簡単に階段室へと侵入していき、一気に全階へと火災が広がってしまいます。
こうなってしまうともう火災は手のつけようがなくなってしまうので、出来る限りその状態を避ける必要があります。
そうした色々な条件を考えた結果として、ちょっと前置きが長くなっていますが、建物の様々な場所で「耐火性能」を持つ壁が必要になってきます。
そうした耐火性能が必要な壁の中には、当然LGS壁も存在するので、そこはLGS壁の仕様を変えておく必要がある訳です。