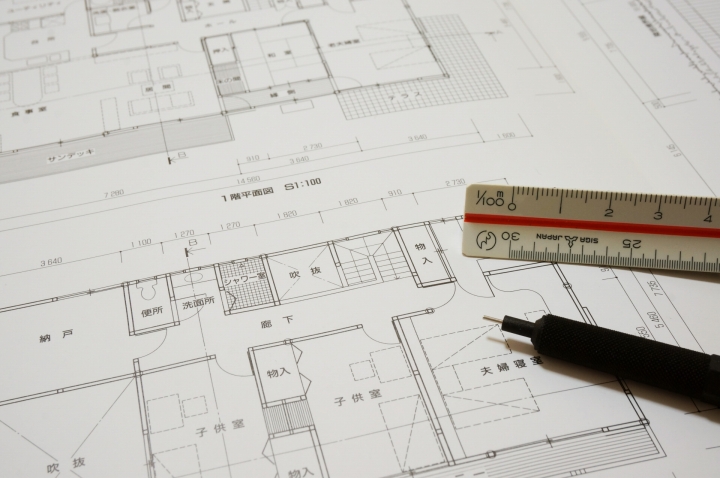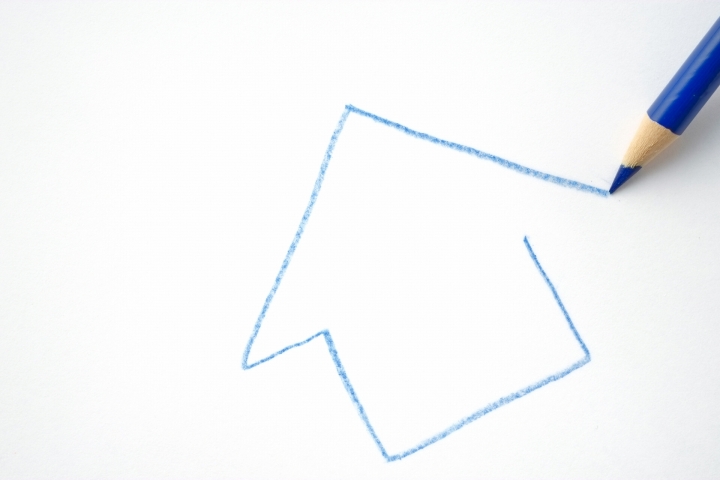どのような建物を計画するのかを計画する役割を持っている設計者、そしてその設計者が作成・発行する設計図。
それに対して施工段階では、発行された設計図通りに建物をつくっていく役割を担っている。
前回はそのあたりの話を簡単に紹介しました。
設計者と施工者との役割はそこで分かれていて、それぞれの立場で良い建物を造ろうとしていく、というような感じです。
設計者が作成した設計図を基本方針として、出来るだけその要望に沿っていて、なおかつ品質の高い建物を低コストで造り上げていく。
これは実際にそう簡単な仕事ではありませんが、それこそが施工者の役割であって、それを実現するあたりが企業の技術力なのでしょう。
施工段階では実際にものを造っていく段階であるため、設計段階よりもさらに具体的な情報が必要になってきます。
なので設計者が作成する設計図に比べると、施工段階で作成する図面というのはもっと細かい部分の情報が表現されることになります。
施工段階の細かい図面にも幾つかの種類がありますが、今回はそれにはどんな種類があるのかを説明してみます。
■施工図
設計者が作成する設計図をベースにして、施工会社つまりゼネコンが自分たちでスムーズな施工をする為に作図する図面を施工図(せこうず)と呼びます。
施工図は設計図をベースにして作成されますが、設計図よりもさらに細かい情報、主に文字情報や寸法が記入されています。
施工図を見れば実際に工事が進められる、というくらい細かい情報を盛り込んでいきます。
なぜ設計図で工事をするのではなく、わざわざ手間と時間とお金をかけて施工図を作成するのかというと、施工段階でトラブルが発生しないように、という目的があります。
出来るだけ具体的に図面上で検討をして、その内容で実際の工事を進めていく。
そうすることによって、予想外のトラブルが発生して工事の手戻りが発生する、というような事態を避けたい。
施工者が管理する大きな要素にコストと工期があります。
トラブルで何度も工事をやり直したりすると、お金と時間がどんどんなくなってしまいます。
そうなると工期に間に合わなくてプロジェクトとしても赤字になって…という仕事としては最も避けたい状態になります。
そうならないために事前に図面で色々と検討をする、というのが施工図の役割です。
建物を構成するには様々なパーツが必要になって来ますが、実際にどんな製品を使うかまで検討して出来るだけスムーズに施工を進めようという目的がある訳です。
そして当然採用する製品がきちんと納まるように、それぞれの部分を細かく調整していくという役割も持っています。
設計図に比べる「なんですか?施工図って」みたいな感じになりますけど、工事現場では結構重要な役割を持っている図面です。
施工図の中にも「仕上図」とか「躯体図」など、さらに細かい分類があるんですけど…
今回はそこまで細かく考えず、設計が作図する設計図に対して、ゼネコンが作図する施工図みたいな認識でOKです。
この施工図をきちんとまとめる為には、設計者の意思である設計図を読みとる能力と、実際の施工についての知識が必要になってきます。
設計図を読んで設計の意図をくみ取り、それを実際の施工で可能か判断して、実際に施工出来るような図面にしていく。
それが施工図に求められる役割です。
施工図を作図する人によってかなり施工図のレベルは変わってくる、というのが色々な施工図を見てきた私の印象です。
施工図は設計者に提出されて、チェックを受けた後に「これで良いです」みたいな許可を得てから施工に入ります。
だから設計者にとっても、施工図というのは非常に馴染みの深い図面だと言えるでしょう。
たまに酷い施工図があったりしますけど、それについてはもう少し後で色々と書ければと思っています。
■製作図
建物を構成する部材や仕上材は様々で、そのあたりの調整を施工図で進めていく、という話を先ほどは紹介しました。
そうして調整していく部材の大半は、工場であらかじめ製作された後で現場に運ばれてきます。

例えばドアとかアルミサッシュなど、金属で出来た部材は工場で精度良く造ってくる方が効率的なんです。
現場で鉄板を曲げてドア枠をたくさん造っていくというのは、必要なスペースとか製作の精度を考えるとあまり現実的ではありません。
もっと現実的な話として、最初から工場で造ったものを現場に運んできて、それを取り付けるだけの状態にしておくことが大事です。
そうすることによって、建築現場で絶対にやらなければならないことと、別の場所でやっても大丈夫なことを区分している訳です。
昔の東京オリンピックでホテルをたくさん建てている時に、お風呂を現場でひとつずつ作っていく時間と手間が惜しいというか、そこまでの時間がなかったことがありました。
その問題を解決する方法として、工場でユニットバスを作って運んできて、現場ではもうお風呂を設置するだけにする、というやり方が採用されました。
今ではユニットバスは当たり前になっていますが、昔は現場でひとつずつ防水をしながらお風呂を仕上げていたんですね。
これは結構大変なことなので、その手間を工場でやってしまうという考え方は理にかなっていると言えるでしょう。
ただ、いくら工場で精度良く造られたとしても、そもそも大きさが違っていたらもうお話になりません。
そんな状況になるとコストがかかるばかり。
それではダメなので、工場で造った部材がきちんと取付可能なように、図面で事前に検討しておく必要があります。
そうした事前検討に必要なのが図面ということになり、特に工場で製作する為に必要な図面を「製作図」と呼びます。
施工者の役割として、そうした製作図にきちんと目を通して、出来るだけ工場で作ったものが無駄にならないようにするという業務があります。
出来るだけじゃなくて、工場で製作してきたものが全て無駄にならないように、と言った方が正解に近いかな。
そして、もう少しこう変えたいなどの要望をメーカーと設計と打合せして、少しでも良い状況に向かって調整していく。
これが建築現場で施工者側が用意する図面で、施工図と並んで非常に重要な「製作図」と呼ばれる図面です。
施工図も製作図も基本的には設計者がチェックをして、問題ないことを確認してから工場で加工を開始します。
なので、たとえ設計が終わって設計図を発行した後でも、設計者の仕事はなくならないんです。