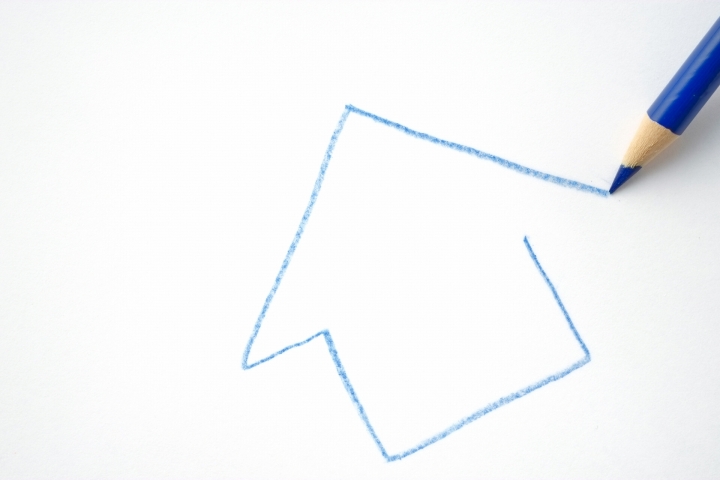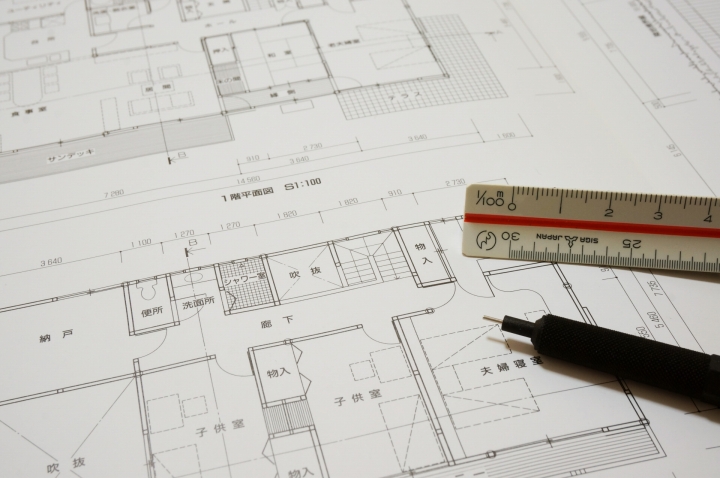建物を計画して実際に造っていくために必要なステップとして、設計段階から施工段階へとステップが進んでいく、という話を前回は紹介しました。
建物をつくっていくための基本的な方針はあくまでも設計図にありますけど、設計図ではそこまで具体的な細かい部分までを表現していない場合が多いです。
そのあたりの情報をもっと具体的にしていくために、施工者側はさらに細かい部分を表す図面を必要としている訳です。
そのために作図されるのが前回紹介した「施工図」と「製作図」です。
施工図はその名の通り、施工をする為の図面ですから、どんな部材を使うかなどの細かい情報が絶対に必要になってきます。
そうした図面を作図するので当然、施工図を作図をする方は、建築の納まりや施工についての深い知識を求められます。
最近はCADで綺麗な図面が描けるようになったので、知識があまり多くない方でも図面を作図することは可能になりました。
最近とは言ってもCADが普及してから20年以上経過していますが…
やっぱり建築の知識や現場の知識がない方が図面を描いたとしても、そこまで気が利いた図面にはならないという現実があります。
「絵に描いた餅」という言葉は、実際には何の役にも立たないことを意味していますが、まさにその状態になってしまいがち。
これはどんな分野でも同じだと思いますが、プロに求められる知識と技量というのはやはり非常に大きなものがあるんです。
と、施工についてはこれで終わりにしておき、今回は最後に挙げた「維持管理」について軽く触れてみたいと思います。
■建物の維持管理について
建物を計画してから実際につくっていく際のステップを簡単に分けていくと、以下のような項目がある、という話を以前に紹介しました。
・設計段階
・施工段階
・維持管理
このステップは間違いではないのですが、当サイトは図面や納まりについての話をメインにしている関係で、最後の「維持管理」はあまり説明することがないんですよね。
建物はもう計画段階を過ぎて、その方針を元にして施工が終わっている訳で、もう建物は出来上がって運用されている訳ですから。
この段階になると、図面を見てどうこう言うよりも、もう実際に出来上がっている建物を見た方が早いということになってしまいます。
だからあまり図面の役割は多くないんです。
なので説明もサラッとで終わろうと思います。
設計が考えたプランに従って、施工が建物を実際に工事していき建物が完成すると、実際に建物を使う方が建物の中に入ってきます。
建物の維持管理というのはそうした段階、建物が完成して実際に使い始める段階でようやく始まります。
これは考えてみれば当たり前の話で、建物が実際に出来上がって使う段階にならない限り、維持管理という概念は必要ないですよね。
基本的に建物の維持管理というのは、建物を建てようと考えた個人や会社、いわゆる施主が受け持つステップになります。
設計者と施工者が役割分担をしながら作り上げて完成した建物を、出来るだけ長期間使えるようにメンテナンスしながら管理していく業務です。
まあ「維持管理」ですから、言葉のニュアンスとしてはそのままですが。
維持管理業務のイメージとしては、なんとなくマンションの管理人みたいな感じに近いかも知れません。
例えば使っていく内にどこかが壊れたら交換などの対処をするとか、急激に劣化しないように建物を綺麗に保っていくとか。
そういう業務ですね。
建物は完成してから少しずつ古くなっていくので、経年劣化する部分、例えば屋上の防水などの部分を定期的にメンテナンスする必要があります。
もちろん何もしないままでも建物が倒れたりすることはありませんが、雨漏りなどのリスクが高くなってしまうので、あまりお勧めすることは出来ません。
車とかバイクなどもこまめにメンテナンスするとずっと快適に乗ることが出来るのですが、それと同じように、建物の寿命はどれだけ手をかけているかによって大きく変わってきます。
そういう意味では、維持管理が担う役割というのは非常に大きなものだと言えるでしょう。

何百年前から建っている寺院などは、やはり定期的にメンテナンスをしてきたからこそ今でも美しい姿を見せてくれているんです。
新しく立てた建物もやっぱり同じ考え方でメンテナンスをしていく必要があるんです。
■竣工図
こうした建物の維持管理について紹介してきましたが、ここまで読んで頂いた方なら分かるように、建物の維持管理業務はあまり図面とか納まりと関わりが多くありません。
どうしてこのステップを紹介したんだろう…という気持ちもありますけど、建物の大きな流れとしてまずは知っておいて頂ければと思います。
ただ、建物の維持管理をする段階で図面を必要とする場合も時々はあります。
例えばどこかが壊れたから直したいとか、雨漏りしているので修理のために建物がどのようにつくられているのかを確認したいとか。
そう言った場面では、施工段階で作成された図面である施工図や製作図を見ることが多いです。
設計図を最終プランに合わせて修正したものを「竣工図」と呼び、建物が竣工した際には、この竣工図が施主に提出されます。
でも、それはあくまでも建物の基本方針である設計図を修正した図面なので、細かい建築的な納まりまでは表現されないのが普通です。
設計図ではそこまで表現しないので、図面としてはそれで不正解という訳ではありません。
これは設計図が悪いとか、そういう意味の話ではなくて、単純に図面の目指す方向性が少し違うだけ。
なので、より細かい部分をを確認したい場合には、同じように提出される施工図とか製作図を見ることが多いです。
そうして細かい部分を確認しながら、必要な修理をしたり、同じ製品を新しく取り付けたりなどの対応をしていく訳です。
建物の維持管理で図面を使うのはそのくらいですが、建物を維持していくためにかなり重要な要素ではあります。
ただ、建築の納まりとはあまり関係ない話になってしまったので、維持管理についての話はこれで終わりにしておくことにします。