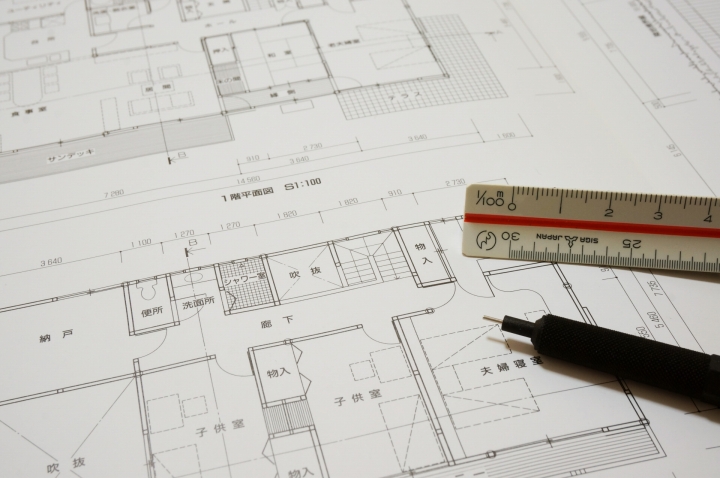当サイト「建築の納まり図とその解説」では、建物を構成する各所の納まり、つまり各所がどのような関係になっているか、というテーマで色々と話をしていきます。
もちろん言葉だけではなかなか伝わらない部分が多くなってしまうので、図面や写真などを交えて解説していこうと考えています。
建物を構成する各所の納まりバリエーションは本当に多岐に渡るので、全部のパターンについて詳しく触れていくのはかなり難しいことかも知れません。
建物の仕上材というのは日々進化していて、安くて見栄えが良くて施工しやすい製品が出てくることも多いです。
なので、それぞれの製品に合わせて納まり詳細図をすべて用意しておくことは、時間という制約がある関係で厳しいという現実があります。
でも、変わっていくのはあくまでも目に見える部分である仕上材だけの場合が多いです。
なので、基本的な納まりの考え方さえしっかりと押さえておけば、あとは表面に施工する仕上材が少し変わるだけ。
であれば表面の仕上材が新しくなった際に、その仕上材の特徴と厚みを知っておき、あとは納まりを応用していけばOKという理屈になります。
そういう考えがあるので、当サイトではまず基本的な部分の納まりについて、出来るだけ分かりやすく解説していこうと思っています。
あと問題になりそうなのは解説する私の知識がどこまでのレベルにあるか、というあたりですが、まあ基本的な納まりなら大丈夫じゃないか。
少しの願望を込めてそんなことを考えています。
そうやって細かい納まりの話をしていく前の段階として、まずはその納まりを表現する「図面」について簡単に触れてみようと思います。
■図面には色々な種類と役割がある
建築の納まりについて図面や写真で色々と解説していく、と簡単に表現してきましたが、一口に「図面」言っても実際には様々な種類があるんです。
そしてその種類によって図面上に表現されるものは色々と変わってきます。
もちろん当サイトは「建築の納まり図とその解説」というタイトルなので、取り扱う図面は基本的に建築関連の図面ということになります。
私は建築関連の図面に関わる仕事をしているので、建築以外の図面については何も説明することが出来ないですし。
ただ、建築の図面というくくりの中でも、やっぱり様々な用途や役割がそこにはあって、そこだけでも結構なバリエーションがあるんですよね…
その図面の種類は、建築の中でどんなファクターというか、どんな段階で作図されるのかによって、かなり大きく変わってきます。
もし今これを読んでいる方が建築に携わっている方であれば、そんなことは百も承知だとは思います。
そして、自分がその段階の中で、どのような部分の図面に関わっているか、という部分についても知っているはず。
なので、今現在建築関連の仕事に就いている方にとっては、これから説明する内容から得られるものはあまりないかも知れません。
でも、まあ説明の最初ということもあるので、まずは簡単にそのあたりについて触れていきたいと思っています。
もし「もう知っている」という方は、少し飛ばして読んでみてください。
ということで、まずは建築の役割分担による図面の種類から。
■建築工事の流れ
一つの建物を計画して、実際にその建物が完成に至るまでに必要なステップは、細かい話をしていくとかなりたくさんあります。
あまりにも細かい話を最初にしても仕方がないので、ざっくりと大きなカテゴリー分けをしてみると、以下のような感じになります。
・設計段階
・施工段階
・維持管理
これはかなり大きなカテゴリー分けになっていますけど…
要するにどんな建物を建てるかを計画していくのが設計段階で、そうして立てられた計画を実行していくのが施工段階、というイメージになります。
最後にある維持管理というのは、建物が完成してからその建物をどのように維持していくか、という段階になります。
この段階ではもう建物が出来上がっている状態なので、建築関連の仕事に就いている方にとってはあまり絡みが少ない段階かも知れません。
図面という視点で見ていくと、建物を作っていくそれぞれの段階によって、必要な図面は少しずつ変わってくるという話があります。
なので、まずはそれぞれの項目について簡単に説明していくことにします。
■設計段階
まずは設計段階ですが、ひとつの建物をこれから建てようとした場合に、まずは必要になってくるのが基本的な計画をつくることです。
実際にどのような建物を建てるのか、という基本方針を作成して、それを煮詰めていくのが設計と呼ばれる行為になります。
建物の基本方針とはつまり、その建物がどの程度の大きさになるのかとか、何階建てにするのかとか、構造はRC造なのかS造なのかなど…
そういった建物を造っていく中で根幹となるような部分をまずは考えていく訳です。
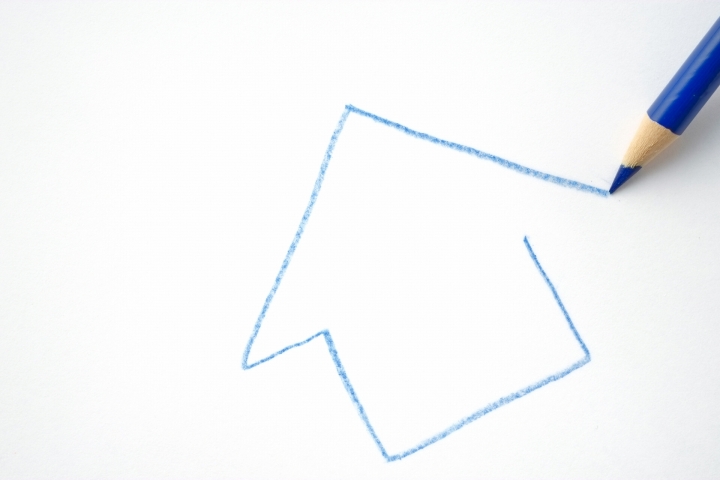
こうした基本が固まっていない段階で、例えば窓の形状をどうするかを検討してもあまり意味がありません。
その前にまずは基本方針を決めておくことが重要になってきます。
こうした建物の基本方針というのは、様々な要素によって色々と変わってくることになりますが、以下に挙げる要素が主な条件になるかと思います。
・建物はどんな用途が求められているか
・敷地の形状や隣接する道路の幅はどうなのか
・どんな地域に建てるのか
・法的な制限はどの程度あるか
細かい点を挙げていくとキリがないですけど、最も重要な要素は「施主がどんな建物を望んでいるか」という部分です。
建物の用途によって施主は様々ではありますが、その建物をつくることによって何らかのメリットを得たいと考えていることに違いはありません。
そうして施主が望んでいる建物を、敷地条件や法的な条件に沿って、最も効率よく建てる為にはどんな形状が良いのか。
そのあたりを細かく検討していき、提案をしたりなどを繰り返して具体的な形を作っていくのが「設計」という業務になります。
建築関連の仕事で「図面」というと、一般的にはこうした設計段階の図面を指すことが多いような気がします。
CMなどでも時々ありますけど、スーツを着た方がヘルメットをかぶって図面を見ている、みたいなシーンがあったら、きっと設計段階の図面を見ているのだと思います。
……この話は次回に続きます。