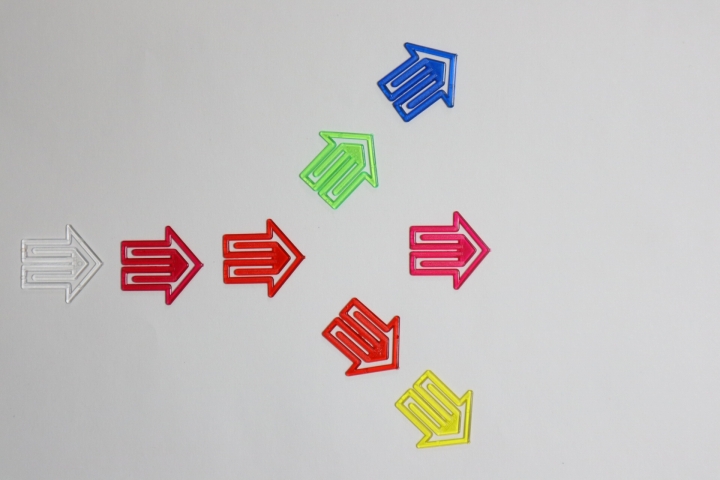設計者は自分達が色々検討や調整をしながら設計する建物に愛着を持っているので、細かい納まりには非常に気を使う場合が多いです。
たとえそにこだわりによって出来上がった部分が、一般の方に目に止まらない部分であっても気になる、というのはプロとして当たり前のことでしょう。
そうしたこだわりが美しい建物をつくっていくんです。
前回はそのあたりの話を紹介しましたが、まあこれはもの凄く一般的というか普通の話であって、別に驚くような話でもないと思います。
もちろん設計者と言っても色々な方がいるので、中には「イメージはこんな感じだから、あとは施工の方で検討ヨロシク」みたいな人もいますけど。
そういう人であっても、あとはヨロシクと言っておきながら、完成形のイメージが違うとやり直しを要求したりします。
最近はそういう「先生!」みたいな設計者を見かけない気もしますけど、これは私の環境の問題かも知れませんね。
まあこのあたりの話はちょっと極端な例ですけど、設計者はそれだけ建物の出来にはこだわっているということです。
程度の差こそあれ、そこは恐らく設計者が共通して持っているこだわりだと思います。
今回はそんな設計者が設計図をまとめた後で、建物の納まりにどうやって関わっていくのか、という部分について簡単に説明してみます。
設計者は設計図を発行したら仕事完了、という訳ではないんですよね。
■設計者のポリシー
今まで話をしてきたとおり、設計者が発行する設計図というのは建物をどのようにつくっていくのかという基本方針を示すものになります。
施工者はその設計図によってコストや工期を検討していく訳ですから、設計図の内容が全てのスタートになるのは当然と言えるでしょう。
設計図が示す情報で重要になってくるのはやはり全体のプランであり、どこにどのような仕上材を採用するのか、そしてどんな構造になっているのかという部分です。
そういう基本的な部分を設計図では優先して表現している為、全ての部分の細かい納まりまでを表現していくのは結構難しいものがあるんです。
時間的な問題があって、要するに全然時間が足りなくて、細かい部分まで色々と表現したくてもなかなか出来ない、という現実もあります。
せいぜい出来るのは、設計図の中に部分詳細図として巻末のあたりに「こんな感じで納めたい」という詳細図を盛り込むことくらいです。
だけどその部分詳細図だけで建物全部の細かい納まりを網羅出来る訳ではない、というのが現実ではないかと思います。
これは設計者が持っている役割を考えると仕方がないと思う部分もあるし、もっと細かい部分も表現した方が良いと思う部分もあって難しいですね。
そうした状態で設計図を発行するしかない設計者が、実際どのように細かい納まりに関わっていくことになるのか。
それは、施工段階で作成する図面、つまり施工図や製作図をチェックをすることで、自分たちの考えやこだわりなどを表現していくことになります。
建物をつくっていくプロジェクトが設計段階から施工段階に進んでくると、施工者は施工図と製作図を作図して設計者に提出していきます。
そこに記載されている内容が設計図と合致しているかを確認するのが設計者の業務なので、膨大な数の図面をチェックしていくことになるんです。
そうした図面をチェックすることによって、細かい部分の納まりを色々と決めていく訳です。
■意匠設計者の現場での役割
設計者から発行された設計図に沿って施工者側が現場を進めていく訳ですが、その進捗や内容を監理する、というのも設計者の仕事なんです。
これは「監理」という別の部署になることが多いですけど、意匠設計者が設計監理責任者である場合も多いので、施工段階でずっと現場にいることも多いです。
もちろん建物の規模によって現場にいるかどうかは変わってきますけど、どこにいたとしても、施工者側から提出される図面の内容は確認していきます。
また、意匠設計者が現場で細かい施工段階での図面をチェックしていく中で、専門業者と打合せをすることもあります。

専門業者というのは、例えばアルミサッシュを製作するメーカーだったり、ユニットバスを製作するメーカーだったりです。
そうした打合せをしていく中で、細かい部分をどうするかという意匠設計としての要望を、図面の中で表現することが出来るんです。
今まで設計図ではなかなか表現出来なかった部分について、施工図や製作図の段階で具体的に、より細かく決めていくことが出来る。
これが現場での意匠設計者の役割になります。
こうした段階があるからこそ、建築の細かい納まりについて設計者が気にしていないはずはない、ということを書いたんです。
こうした打合せや調整の段階で、きちんとした意匠のポリシーを示すことが出来れば、それが余程無理難題ではない限り実現されます。
もう少し詳しく書くと、設計図に全く記載のない納まりで、なおかつ余程コストが高くなりすぎない限りは、ということになります。
施工者側は設計図を元にコストを算出して見積もりをしている訳ですから、全然設計図に記載されていないことはコスト的に出来ない場合も多いです。
しかし施工者側も出来るだけ良い建物を造りたいと思っているので、あまりコストに絡まない部分でより良い納まりの方針が設計者から要望されれば、それでやりましょうとなります。
このあたりは打合せの中で色々な要素を含めて駆け引きされたりもします。
大抵の意匠設計者は、自分が設計した建物をどう納めるのか、細かい部分まできちんとした考えを持っています。
先ほども書いたように、それが大幅なコスト増にならない限りは、基本的に設計者の意見が尊重されます。
もちろん施工者側も言われっぱなしではなく、それはやるけどこっちは施工者側の要望を通したい、みたいな話もあります。
このあたりの話が建物を造っていく中で一番面白い部分かも知れません。