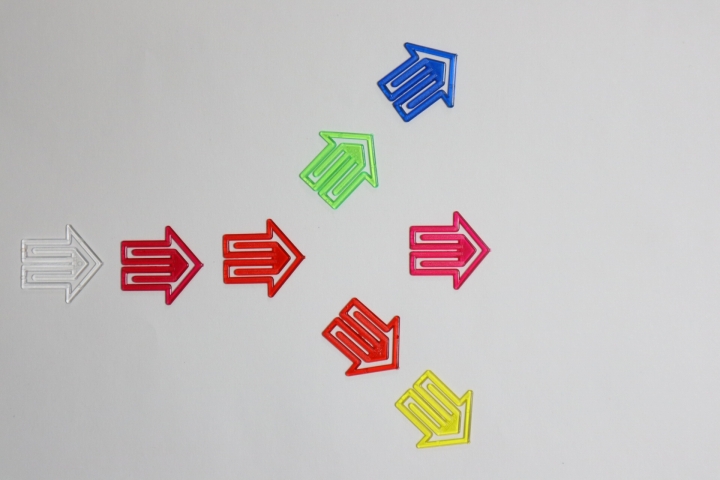設計者が建物の納まりに対して持っているポリシーに対して、実際に建物をつくっていく立場である施工者側がどんな視点を持っているのか。
前回はそのあたりについて考えてみました。
施工者は工期を守りつつ利益を出すことを求められているので、複雑でお金がかかるけれど最終的には綺麗に見えるというような納まりには賛成しにくい立場なんです。
ただし施工者がコストを気にしているからと言っても、最終的に見え方や納まりはどうでも良いと思っている訳ではありません。
むしろ設計者があまり気にしない「これで施工が出来るのか」とか「人が入っていけるのか」などに気を配っていくことになります。
建物のデザインは確かに良いけれど、実際には人の手が届かないから施工出来ないとか、後で壊れてしまう危険があるようでは困ります。
そうしたことにならないように、意匠性も重視しつつ、コストと施工性にも気を使うのが施工者の立場なんです。
そして建物が完成した後でも困らないような、使い勝手の良い建物をつくっていくことを意識している場合が多いです。
最初は見た目が良くても、すぐに雨漏りするような納まりでは困る訳です。
施工した建物で雨漏りがあった場合、設計者と施工者とでどちらが施主から呼び出されるかというと、やはり施工者なんですよね。
そう言った意味でも、設計者と比べると施工者の方が、特に外壁や水廻りの納まりについてシビアに見ていく傾向にあります。
誰だって大雨の後で呼び出されて謝るのはイヤですから。
設計者と施工者とでどちらの視点が優れているのか、とかそういう問題ではなくて、これは単純に立場の違いがあるだけ。
どちらもその建物のクオリティを高めようとしていて、そのアプローチが少し違うだけの話です。
■実際に施工が出来ない場合も
先ほども書きましたが、施工者が納まりで気にする項目として、コストの他に「実際に施工出来るのか」という部分があります。
これは実際に工事を進めていく施工者らしい視点であって、建物をつくっていく上で非常に重要なことだと思います。
設計図に記載されている内容が必ずしも現実的である訳ではなく、時には施工可能な状態ではない場合もありますから。
・狭すぎて人が入れないなどの物理的な問題
・存在しない商品サイズが選択されている場合
など、施工が現実的ではない理由は幾つかありますけど、施工出来ない状況のまま工事を進める訳にはいきません。
一番困るのは、図面上の話でずっと計画が進んでいて、いざ施工をする段階になって「これは出来ない」となることです。
そうなってしまうとやっぱり時間が無駄になってしまうので、図面上でそうした部分がないかを確認していき、やり方をどこかで変更しなければなりません。
そのあたりも施工者側の役割になります。
ただ、単純に「施工が出来ない」と言っても、そこには幾つかのニュアンスがあります。
そのやり方だと大変だから出来ないと言うのか、お金がたくさんかかってしまうから出来ないと言うのか、本当に物理的に不可能なのか。
そのあたりのニュアンスは様々です。
一般的な話をすれば「お金に糸目を付けなければ大抵のことは実現出来る」という話もあります。
そのあたりの話は設計者も施工者も充分に承知しているんですけど、問題は本当に実現出来るかどうか、という話ではありません。
そこまでコストをかけて施工をするような場所なのか、そのメリットがどこにあるのか、ということを設計者も施工者も考えている訳です。
ちょっと納まりを変えればスムーズに施工が出来て、それでも最終的に見た目は大きく変わることはない、というような納まりを選んでいくのがベストです。
設計者と施工者とで見ている部分は少し違っていますが、設計者が見ている部分も施工者が見ている部分も、どちらも重要なところなんです。
そのあたりのすりあわせを打合せでやっていく、という感じです。
■打合せの繰り返し
そうした複雑な部分の納まりについては、施工者側の意見として、設計者に「これは実際施工が難しいのでこう変えたい」という話をすることになります。
設計者も素人ではないので、施工が難しいというのは聞けばすぐに分かります。
だったらどうやって進めるのが良いのかとか、どんな状態であれば施工可能なのかなど、細かい調整をしながら施工を進めていく。
建物をつくってく現場の基本的な流れはこんな感じです。
こうした設計者と施工者との打合せは、出来るだけ質の高い建物をつくっていく、という共通の目的があって行われます。
設計者も当然コストは意識していて、同じような見映えになるのなら、コストが掛からない方を選びたいと考えます。
もちろんどうしても意匠設計者として譲れない部分もあって、そこはある程度コストがかかってでも施工をやって欲しい、という部分もありますけど…
それは意匠設計者のポリシーだし、そうした大事な事は絶対に設計図に記載してありますから、コスト増という話にはならないはず。
建物を施工している段階では、設計者と施工者との打合せは色々な部分について何度も何度も繰り返されることになります。
そして出来るだけお互いが納得するような納まり、施工方法を煮詰めていく訳です。

設計者としては、もうすでに設計図は完成している訳ですから、施工段階での設計者の仕事は殆どがこうした打合せになるんです。
そうやって少しずつ建物の完成度を高めていく訳です。
これは設計図をまとめている段階よりもリアリティがある業務なので、やっぱり面白みがある業務ではないかと思います。