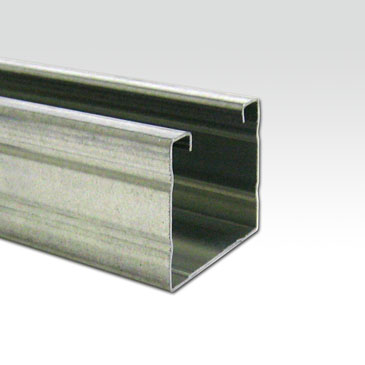前回の説明では、建物を構成する壁のひとつである木下地壁がどのような特徴を持っているのか、という部分について考えてみました。
壁の種類には色々あって…という話で、それぞれの特徴や納まりなどについて今まで説明をしてきました。
そして、前回までの話で取り上げてきた木下地壁で、ひとまず大雑把な壁の分類とその特徴についての説明は終わったかなと思います。
と言ってもかなり大雑把な説明ではありますが…
もっともっと細かい部分について考えていくと、まだまだ色々と説明していきたい内容はたくさんある、というのが事実です。
しかし最初から細かい部分にフォーカスして話をしていくと、なかなか話が進まないんですよね。
まずはざっと全体的に説明をしていき、その説明が一通り終わったかなという状態になったら、足りない部分についてもう少し詳しく説明をしていく。
そんな説明の進め方が分かりやすいのではないか、と当サイトは考えています。
説明している私もその方がやりやすくて、きっと読む方にとっても分かりやすくなるはず、ということで話を進めていきます。
木下地壁が具体的にどのような場所で使われるのか、という話を少しここで考えてみると…
木下地壁はコストや壁厚、そして持っている壁の性能から、マンションやホテルなどの独立した部屋の内部で、間仕切りとして使われることが多いです。
マンションの場合で考えてみると、例えば502号室と503号室は別の住戸になっていて、当然異なる家族がそれぞれ住む場所として使うことになります。
そうした住戸同士を区切る壁については、遮音性能が必要になるし、場所によっては耐火性能も必要になってくるため、RC壁やある程度の性能を持ったLGS壁が採用されます。
隣の住戸の会話が丸聞こえになるマンションとかイヤですよね。
それは誰もがそう思うので、マンションを販売する側、もしくはマンションを貸す側はそうしたお客さんのニーズに合わせた住戸を用意する訳です。
しかし502号室の中で、例えば居間と寝室を区切る壁については、同じ家族が使う部屋ということになるので、そこまでの遮音性能は必要ありません。
そうした住戸内部の間仕切り壁は木下地壁でつくられる場合が多い、という感じです。
同じ壁でも求められる性能が場所によって違うので、それぞれ求められる性能を満たしつつ、出来るだけコストを抑えることを考えた結果そうなる訳です。
今現在、私は自分の書斎でこの文章を書いていますが、隣の部屋である寝室との間にある壁は木下地壁で出来ています。
木下地に対して石膏ボードを1枚しか張っていないので、文字入力をする際にキーボードを叩く音が寝室に結構聞こえてくる、という問題はありますが…
それでもコストメリットはそれなりに大きかったので、今さら音楽やキーボードの音が響いてうるさいと苦情を言うわけにもいかない状態です。
私は騒音を発する側なので、苦情を言うというか、苦情を受け付ける側なのであまり偉そうなことは言えませんが…
同じ壁でも種類によってかなり性能が違う、という話を自宅でも実感しています。
壁の種類や性能についての大まかな話はこれで終わりとなるため、今回は最後ということで簡単に全体をまとめてみたいと思います。
■求められる性能を考える
壁には色々な種類がある訳ですけど、それぞれの壁が求められる性能というのは場所によって様々ということになります。
もう少し具体的な表現をすると、壁には大きく分けて以下のような性能が求められます。
・水を通さない(止水性能)
・火災の際に火を一定時間遮断する(耐火性能)
・音を漏らさない(遮音性能)
・視線を区切る
それぞれの部屋を区切る壁ごとに求められる機能があるので、コストをにらみつつ求められる性能を満たした壁の仕様を決めていく、という感じです。
例えば外壁であればまずは水を通さない性能が必要になって、それににプラスして、外からの視線を切る為の性能が求められたり。
外壁の場合は室内から外が見えるとか、光を室内に取り込む、という性能が求められることも多いので、その場合は窓を設けたりもします。

また内部の壁を考えると、例えばトイレなどでは音を漏らさない性能が必要になり、当然ですが視線を切る性能も必要になります。
あとは建築基準法によって定められていますが、色々な条件によって一定時間以上の耐火性能が求められる壁も出てきます。
基本的に階段室やエレベータなど、各階がつながっているような場所には「竪穴区画」という防火区画が必要になります。
その為、壁には決められた時間の耐火性能が必要になり、エレベータなどでは音を遮断する性能も同時に求められたりします。
こうした話はごく一部の例で、建物にはそれぞれの場所によって、求められる壁の性能が色々と変わってくるという話でした。
そうした性能の満たして、なおかつコストや施工的に有利な壁は何か、ということを考えていき、採用する壁を決めていく。
設計者に求められるのはそうした仕事ですから、壁について一通りの特徴と納まりを知っておく必要がある、ということになります。
この後からは個別にもう少し細かい話をしていくつもりなので、興味のある方はぜひ読み進めて頂ければと思います。